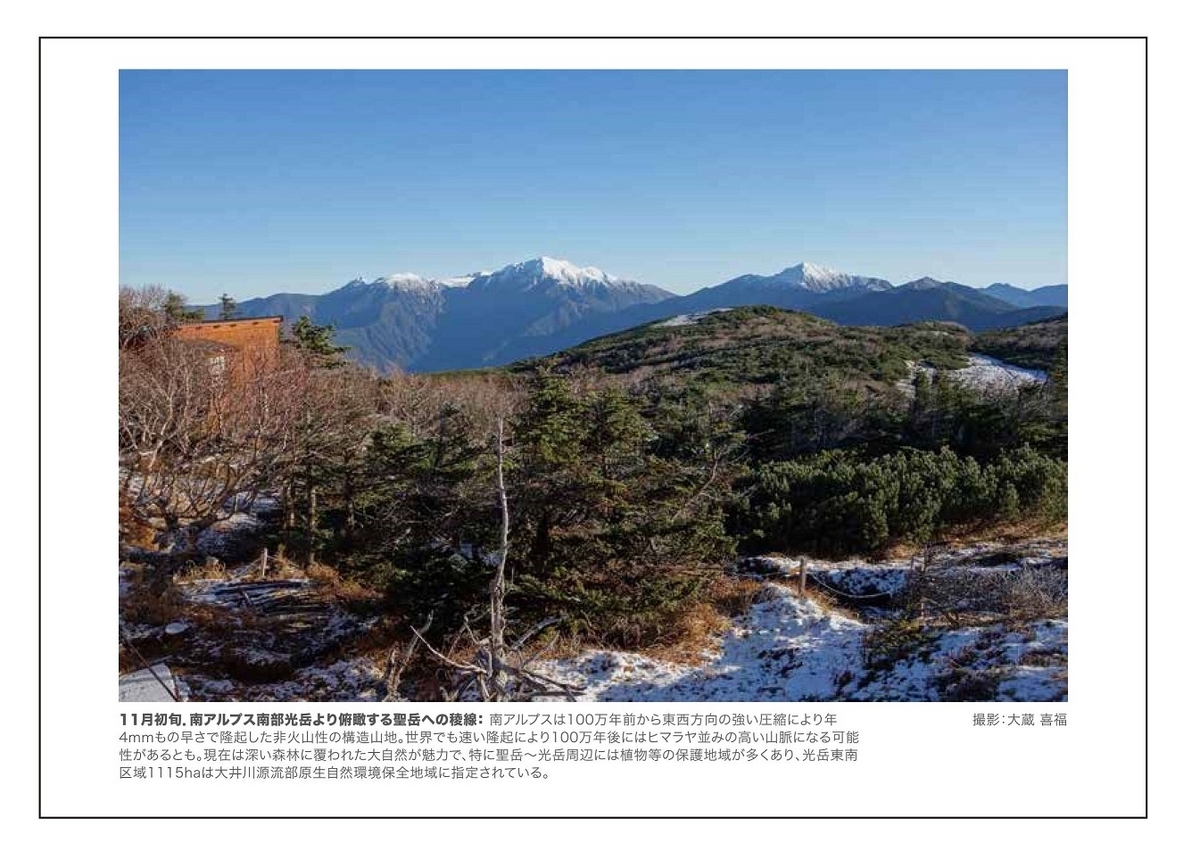2023年10月22日・首都圏現地講座/石井誠治先生
10月22日は石井誠治さんのご案内による現地講座「お茶の水~上野:秋の樹木・植物を観察しながら江戸情緒を感じましょう」を実施しました。
文句のつけようのない秋晴れ!! 青空が高くきれいです、
 2023年10月22日現地講座・神田明神
2023年10月22日現地講座・神田明神天高く、馬肥ゆる秋。神田明神の「明(あかり)」号も毛艶よく!お元気そうでした。あいかわらずかわいい;
さて、今回の現地講座は 本郷台の台地の縁を歩きながら、太田道灌の時代からの江戸城を感じながら、観察をしていく、という趣向です。
聖橋のたもとには、太田姫稲荷神社(一口稲荷神社,いもあらいいなり)の元宮があります。もともとはこの 駿河台淡路坂にありました。きょうご参加の皆さんは、湯島聖堂とは神田川を挟み向かい側に位置していることがよくわかったと思います。大正期に総武線が通るときに工事のため駿河台に移転しています。
 20231022_新旧_太田姫稲荷神
20231022_新旧_太田姫稲荷神移転後の 太田姫稲荷神社の近くの道は「駿河台道灌道」と名付けられていて、駿河台の名を冠した「駿河台匂さくら」というサクラが街路樹として植栽されています。
幕府の学問所であった湯島聖堂で大切にされているのは 孔子の霊廟に植えられている「カイノキ・楷の木」です。種子を中国から持ち帰って、大切に増やして植栽されたそうです。
 20231022_湯島聖堂のかいのき
20231022_湯島聖堂のかいのき歴史を感じられる風情をあちこちに感じながら 歩いて行きました。急な坂の多い地形もよくわかります。
湯島天神では菊の祭典がひらかれるようで、準備が進められていました。
 20231022_湯島天神_菊の鉢
20231022_湯島天神_菊の鉢その後、上野公園方面へ、岩崎邸をとおって不忍池へ。
清水観音堂で「月の松」を見学しました。月の松は以前は池の畔にあったそうですが 舞台にみたてたお堂の近くへ 10年ほど前に植栽され直されたそうです。
 20231022_寛永寺の月の松
20231022_寛永寺の月の松フィナーレには、ちょうどお花がきれいに咲いているジュウガツザクラを観察しました。
 上野公園のジュウガツザクラ(2023年10月22日)
上野公園のジュウガツザクラ(2023年10月22日)ジュウガツ(10月・秋)にも咲くためこのように名がつけられていますが、実際には厳冬期以外は秋から春まで断続的に咲き続け、実は春季に最も多くの花をつけるそうです。この時期はハイライトを浴びますが、春になると他のサクラに埋もれて目立たなくなってしまう... なんだか人間社会を彷彿とさせるようです(??)
さてさて、この日もあっという間に 時間がたってしまいました!
西郷さんの銅像の前で無事に解散、となりましたが アメリカデイゴの木にあるトゲなどを観察しながら、名残惜しく思いつつ; お散歩を続ける方、お帰りになる方といろいろのようでした。
観光客の方も多く、道も歩きにくいところなどもあったとは存じますが、みなさまの協力のおかげで、今回も楽しい現地講座となりました。
ご案内くださった石井誠治さん、スタッフの皆さん、ご参加のみなさま ありがとうございます。